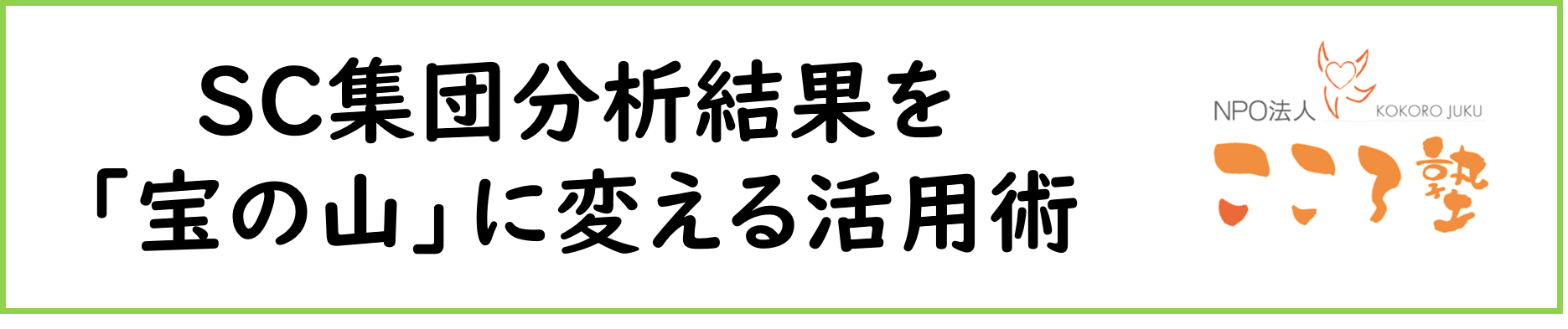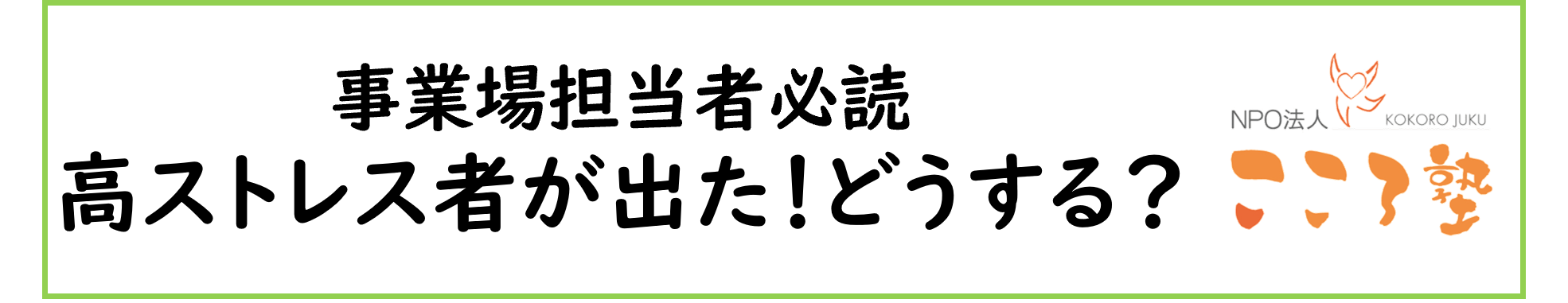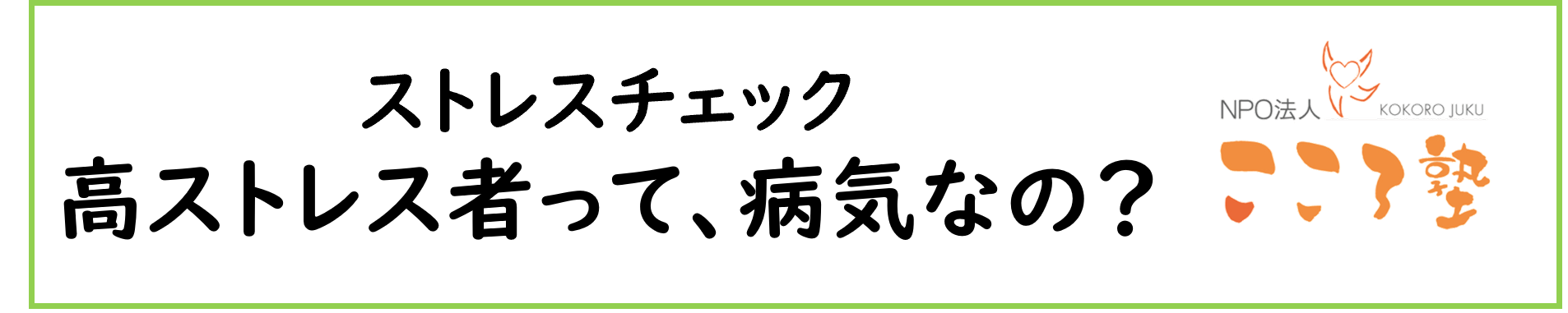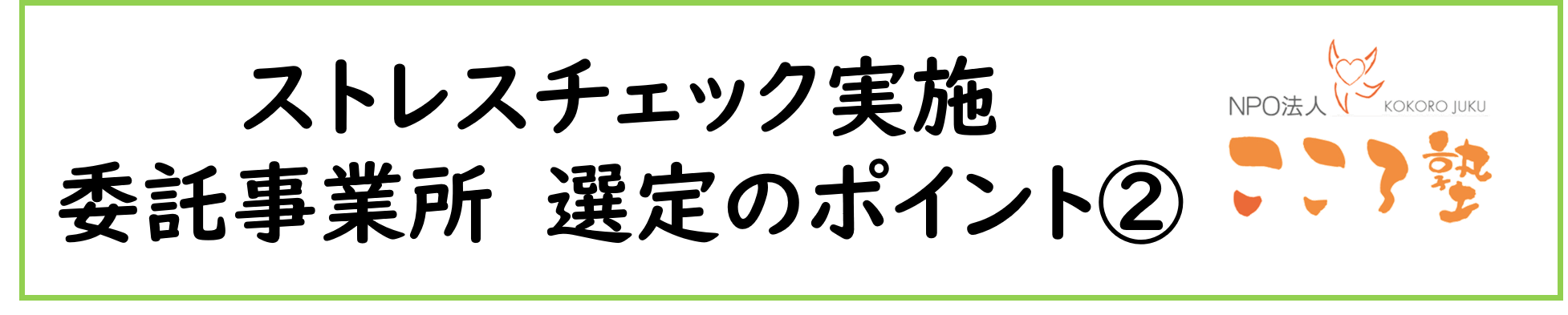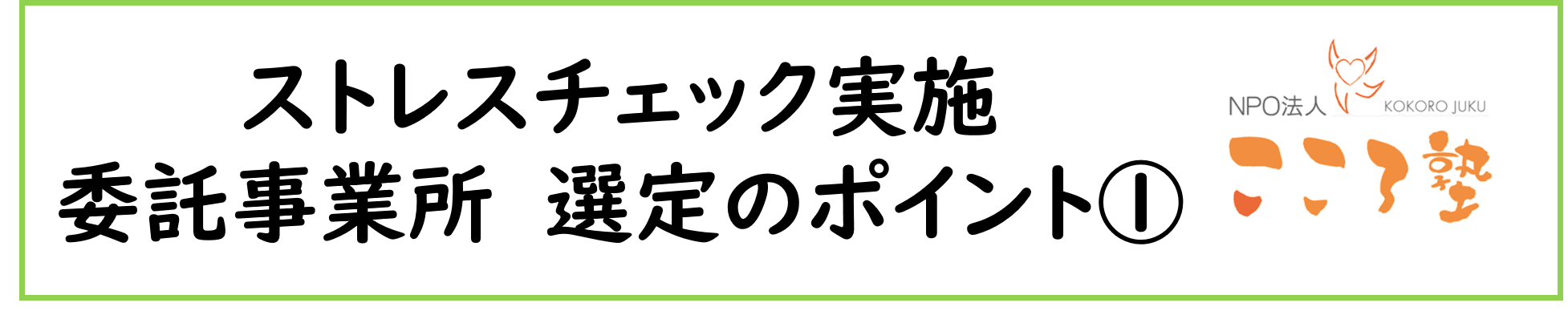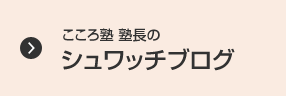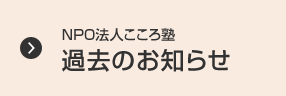その他のお知らせ・報告 · 2026/02/05
集団分析は、職場の「健康状態」を映し出すレントゲンのようなもの。
異常が見つかったときに、どんな「治療(=改善策)」が効果的なのか、前回に引き続き事例をご紹介します。
その他のお知らせ・報告 · 2026/01/22
集団分析は、職場の「健康状態」を映し出すレントゲンのようなもの。
異常が見つかったときに、どんな「治療(=改善策)」が効果的なのか、3つの代表的な事例をご紹介します。今回は2つです。
その他のお知らせ・報告 · 2026/01/08
ストレスチェックを実施した後、その結果を「個人への通知」だけで終わらせてしまうのは非常にもったいないことです。
組織全体の健康状態を映し出す「集団分析」こそ、職場環境を劇的に改善するためのヒントが詰まった「宝の山」! その活用方法をお伝えします。
その他のお知らせ・報告 · 2025/12/25
ストレスチェックの個人結果が返ってきたときに、『高ストレス者判定』だったら、どうしたらよいのでしょうか。
不安に思うことかもしれません、何ができるのかを知って備えておきましょう。
その他のお知らせ・報告 · 2025/12/11
ストレスチェックを実施した後、の『高ストレス者だったので面接をしたいです』と申し出があった場合、事業所としてすべき対応を知っていますか?
流れとポイントを押さえておきましょう。
その他のお知らせ・報告 · 2025/12/04
「ストレスチェックの『高ストレス者』って、病気なの?それならば職場に知られたくない…」と感じる方が多いようです。高ストレスと判定が出た場合は、それは心身のイエローカードです。受け止め方、考え方をお伝えします。
その他のお知らせ・報告 · 2025/11/20
「ストレスチェックの実施に対して費用がかかるのに、集団分析まで必要なのか」と検討されている事業主様も多いと思います。今回はメリット・デメリットを整理し、職場として費用対効果を得られる導入へのポイントをお伝えします。
その他のお知らせ・報告 · 2025/09/25
ストレスチェックの実施に対して費用対効果を取ることも事業所としては大事なことですね。
集団分析とその読み解き、高ストレス者への対応など、委託策を検討するときは、ストレスチェック実施に付随するサポート体制なども確認しましょう。
その他のお知らせ・報告 · 2025/09/11
ストレスチェックを実施したいが、事業場内では難しい場合、外部委託先を探すことになります。
色々なサービスや事業所がありますが、法令に則って、安心安全に実施できる相手を探したいですね。
そんな委託先の事業所選びのポイントを押さえましょう。
その他のお知らせ・報告 · 2025/08/28
ストレスチェックを実施する場合、産業医の選定が義務ではない従業員数が50人未満の事業所では誰が実施者をすればよいのか悩みますね。
2025年8月現在で、どのように進めればよいかをまとめました参考になさってください。
私たちは、ひとりひとりが笑顔で暮らせるように、
こころの健康づくりをサポートします。
NPO法人 こころ塾
愛媛県松山市大街道3丁目2番地16
TEL:089-931-0702(代表) TEL:089-915-1556(企業サポート)
TEL:089-931-0702(代表)
TEL:089-915-1556(企業サポート)
お電話受付時間:平日 10:00~15:00 / 土曜 9:00~12:00(要予約) / 日曜・祝日休み