50人未満の事業所でも義務化が決定したストレスチェック制度ですが、
いつから・どのように等の詳細はまだ発表されていません。
しかし
大きな流れや注意点は変わらない可能性が高いため、今回は現時点(2025/5)で実施義務の対象である
「常時50人以上の労働者を雇用する事業場」のストレスチェックについて解説します。

←これは厚生労働省が推奨している実施手順です。
厚生労働省 こころの耳
「ストレスチェック制度 導入マニュアル」より
この一連の実施手順を以下の3点を踏まえながら実施します。
★毎年1回、すべての労働者に対して実施すること
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
★実施状況は毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する
義務がある
★個人情報の取り扱いに十分注意する
〈導入までの準備〉
・会社として「ストレスチェック制度を実施する」という方針の表明を行う。
「メンタルヘルス不調の未然予防とより良い職場環境づくり」などの目的も併せて伝えると良い。
・衛生委員会等で、実施方法などを話し合う。
誰が・いつ・どのように等々、話し合いの議事録も各事業場できちんと残しておく。
・社内規定として明文化し、職場で周知する。
・実施体制や役割分担を決める…別の記事で解説します。
〈実施の流れ〉
労働者に回答してもらう
・国が推奨している57項目の質問票を使うことをお勧めします
・追加23項目と合わせた80項目は職場の健康診断としても使えます。
・紙を用いた質問票での受検、オンラインでの受検、オンラインと紙の併用など
事業場に合った方法で行いましょう。
質問票を回収する
・実施者、実施事務従事者が回収しましょう。
・人事権を持つ職員や第三者が、記入・入力が終わった質問票を閲覧することは禁止です。
ストレスの程度を評価し、通知する
・実施者が高ストレスで医師の面接指導が必要な人を選別します。
・実施者から本人に結果を通知します。
〈実施後の対応〉
情報の管理・保存
責任者(実施者、実施事務従事者)を定め、鍵やパスワードなどを用いて
個人情報として厳重に管理・保存をします。
・事業場では、集団分析結果、本人の同意のもと提供された個人結果、
同意書、面接指導の結果類を5年間保存します。
※基本的には、個人結果は企業には返ってきません。
医師による面接指導の実施
・本人が希望する場合、産業医等の医師による面接指導を受けることができます。
・本人の申し出は結果通知から1カ月以内に行います。
・本人の申し出から1カ月以内に面接指導を行います。
就業上の措置を行う
・事業場は、面接指導を行った医師から就業上の措置の必要性の有無と意見を確認します。
・就業上の措置を実施します。
面接指導の結果を保存する
・面接指導の結果は事業場で5年間保存をします。
〈結果の活用〉
集団分析を行い、その結果を職場環境改善の取り組みに活用しましょう。
・個人特定ができない単位での集団分析であることが必須
★こころ塾では、厚生労働省の集団分析に加え、
詳細な集団分析結果や経年変化のグラフなどもご用意できます。
データをもとに、より効果的に職場環境改善を行いましょう。
〈実施に当たっての注意点〉
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、
不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、
適切な対応や改善につなげられる仕組みです。
気をつけるポイント
◆プライバシーの保護
◆不利益な取り扱いの防止
受検者が安心して回答できるように、
きちんと制度を理解してから実施すること、
そして個人情報の取り扱いや、制度や体制についてを
労働者に丁寧に周知して実施することが重要です。
今後は、「実施体制や役割分担」や「義務化拡大の詳細情報」が公表されたら
その導入についてなども解説したいと思います。
ストレスチェック制度実施義務の対象事業所が、常時50人以上の従業員を労働者を雇用する事業場から、50人未満も含むすべての事業場に拡大されます。
施行はいつからか、対象者は誰なのか、何をすればいいのか、産業医がいない場合の実施者や医師面接をどうするか、集団分析の読み解き方とその活用などをこころ塾と学びませんか。
また、こころ塾は、ストレス対処やメンタルヘルスケア、職場の取り組みサポートをしています。メンタル不調を未然予防して高ストレス者割合を減らしたり、休職や退職を減らしましょう。地元愛媛・松山で顔が見える丁寧なサポートを行います。こころ塾のEAP・従業員支援プログラム、外部相談窓口、ストレスチェック、高ストレス者面談、研修・セミナー、職場復帰支援について、お気軽にお問い合わせください。

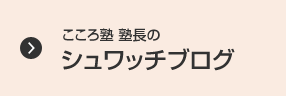
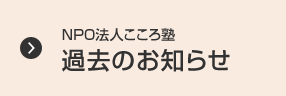


コメントをお書きください