「新入職員向けフォローアップ研修」は、入職して半年前後の時期に行うのがおすすめです。
春の新人研修では、セルフケアやコミュニケーション、社会人としての心構えを中心にお話しします。
なぜなら、社会人は毎日きちんと仕事をしてパフォーマンスをキープすることも仕事の一環だからです。
では秋以降に行うフォローアップ研修には、どんなポイントとメリットがあるでしょうか。
まずは、慣れてきたころに崩れ始める生活リズムを考えます。
同じく、蓄積疲労をケアするためのセルフケアを確認するのも大事です。
そして、周りが見えるようになってきたからこそ大きくなりうる
人間関係やコミュニケーションのストレスを、どのように対処するかを考えます。
それには、
認知行動療法のエッセンスを含んだ「物事の捉え方の癖を緩やかにすること」や
自分や相手のコミュニケーションタイプを知り、互いにストレスが少ないやり取り方法を学ぶ
などが含まれます。少し例を見てみましょう。
◆物事の受け取り方のクセを知る
〈内容例〉

・自分の受け取り方でストレスを大きくも小さくもできる…
例えば、OJT担当の先輩が常に忙しい人で話しかけにくい、
話しかけてもバタバタして聞きたいことが聞けない という場合
『また慌ただしい中で話しかけて嫌がられた』
『忙しそうだ、今はダメかな…』
と遠慮や委縮をしていると、仕事にも影響が出てきます。
「せっかく話しかけたのに冷たかった」と落ち込むより、
次の時には「どう話したら、手短に聞きたいことの確認が
できるだろうか」と考えた方がよいですね。
意識するポイントと、出来事に向き合う柔軟性をあげましょう。
◆行動様式とコミュニケーションタイプ
〈内容例〉

・自分にも相手にも、コミュニケーションのクセがある
コミュニケーションのクセは人それぞれです。
大きく4タイプに分類することができますが、
ご自身のタイプを知っていますか?
(必ずどれか一つというわけではありません)
自分のタイプを知り、相手のタイプの予測がつけば
より円滑なコミュニケーションを試みることができます。
例えば、コントローラータイプの人にサポータータイプの人が話しかける際、
「Aさんはこう言っていて、Bさんはこう言っていて、Cさんは…」と続けてしまうと、
おそらく、「で、結論は?要点を絞って話してください」と言われてしまいます。
「皆さんそれぞれの思いがありましたが、〇〇に決まりました。気を付けておくことは△の点です。」
と結論から話して、補足説明を求められたら、そこで付随情報を伝える方が相手が聞きやすくなります。
春の「まず職場に慣れる」という談会はもう終わり、
これからは「仕事をする」「そのために職場での人間関係をしっかり築く」ということが大切です。
普段からしっかりコミュニケーションを取り、互いに信頼関係を持てるようになることが、
風通しがよく、困ったときに助け合える良い職場になるためのキーワードです。
職場全員が「より良い今日」を目指してお仕事されているはずです。
こころ塾は、なりたい自分、チームの戦力に慣れる自分を目指して
頑張る皆さんの応援団です。これからも一緒に頑張っていきましょう!

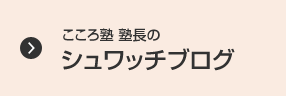
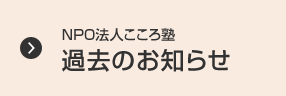


コメントをお書きください